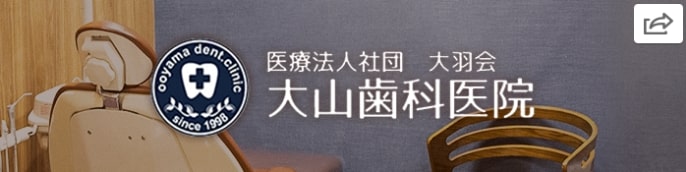― 態癖(たいへき)と顎関節症の深い関係 ―
こんにちは、ソアビル歯科医院です。
「口を開けるとカクッと音がする」「顎がだるい」「朝起きた時に顎が痛い」――
そんな顎関節の不調でお悩みの方、実はとても多いんです。
そして、その原因の一つに最近注目されているのが、**「態癖(たいへき)」**です。
今回は、「顎関節症」と「態癖」の関係について詳しく解説します。
◆ 顎関節症ってどんな病気?
顎関節症とは、顎の関節やその周囲の筋肉に不調が起こる病気で、以下のような症状があります:
- 顎を動かすと音がする(関節雑音)
- 顎が痛む(関節痛・筋肉痛)
- 口が開きづらい(開口障害)
- 食事中に顎が疲れる・だるい
実は、20~40代の女性に多い傾向があり、軽度も含めると日本人の約7割が一度は経験すると言われています。
◆ 態癖が顎関節症を引き起こす?
「態癖(たいへき)」とは、無意識に行っている口や顎、姿勢の“クセ”のこと。
この態癖が、顎関節症の発症や悪化の大きな原因になっていると考えられています。
よくある態癖とその影響
| 態癖の種類 | 顎関節への影響 |
|---|---|
| 頬杖 | 顎を一方向に圧迫し、関節や筋肉に左右差を生じる |
| うつ伏せ寝・横向き寝 | 関節に偏った圧がかかり、変位を起こす |
| 片側噛み | 筋肉の使い方が偏り、顎のズレが生じやすい |
| 歯の接触癖(TCH)・食いしばり | 顎の関節と筋肉に持続的な負担をかける |
| 猫背・スマホ姿勢 | 頭部が前に出て顎が後退し、関節の圧迫が起きやすくなる |
これらの習慣はすぐに症状を引き起こすわけではありませんが、時間をかけてじわじわと関節や筋肉に影響を及ぼします。
◆ なぜ“クセ”が関節に影響するの?
顎関節は、非常に繊細な構造でできています。
少しのズレや力の偏りでも、「関節円板」と呼ばれるクッション構造が正常な位置からずれたり、筋肉のバランスが崩れたりするのです。
また、**上下の歯が触れている時間が長い(TCH)**と、顎の筋肉が常に緊張状態となり、関節にも負荷がかかり続けます。
◆ どうすればよくなるの?
まずは、自分の態癖に“気づく”ことが大切です。
- 頬杖をやめる
- 寝姿勢を仰向けに近づける
- 歯が当たっている時間を減らす(TCH対策)
- 姿勢を意識する(頭を前に出さない)
加えて、歯科医院での適切な診断と、必要に応じたスプリント(マウスピース)治療や生活指導が効果的です。
◆ ソアビル歯科医院での取り組み
当院では、初診時の検査で顎の状態、関節の動き、噛み合わせ、そして生活習慣(態癖)までトータルに評価しています。
- 顎関節や筋肉の触診
- 開口量・顎の動きのチェック
- 姿勢や癖の聞き取り
- 必要に応じて咬合治療・スプリント療法も提案
患者さん一人ひとりの原因にあわせて、無理なく改善できるようにサポートしています。
◆ まとめ:クセを変えることが、顎の健康を守る一歩に
顎関節症は、「噛み合わせの問題」だけではなく、日常の習慣が深く関わる病気です。
日々の小さな“態癖”が積み重なって、思わぬトラブルを引き起こすこともあります。
顎の違和感、痛み、音が気になる方は、お気軽にご相談ください。
ソアビル歯科医院では、包括的な視点からの診療を通じて、よりよいお口の健康をサポートします。