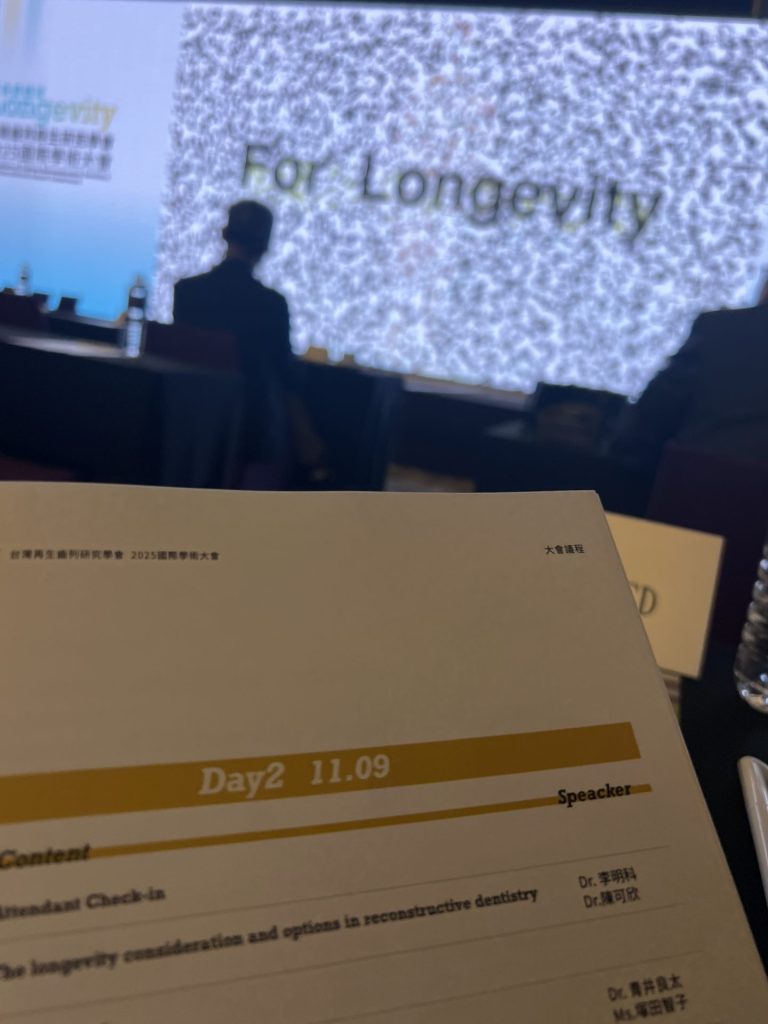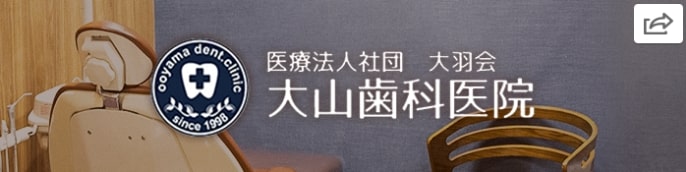こんにちは、ソアビル歯科医院の鈴木です。
先日に続き、台湾で開催された「台湾歯列再生研究学会 2025国際学術大会」に参加した二日目の内容をご紹介します。
今回の大会テーマは 「長期安定(Longevity)」。
歯科治療は「治す」ことが目的ではなく、治療後の状態を10年、20年というスパンでどう守り続けるかが本質であるという考えが全体を通して共有されていました。
私は、日本包括歯科臨床学会(JACD)のメンバーとして、
「包括的な診断と治療計画」
「咬合の再構築」
「補綴・インプラントの長期管理」
といったテーマを日々研鑽していますが、今回の国をまたいだ議論の中でも、共通の価値観が明確に存在していると強く感じました。
Day2の主な講演内容
| 時間 | 演題 | 主なテーマ |
|---|---|---|
| 09:00〜10:00 | The longevity consideration in reconstructive dentistry | 長期を見据えた補綴計画 |
| 10:30〜12:30 | Longevity in implant treatment / Maintenance | インプラントを守る設計とメインテナンス |
| 13:30〜17:00 | Material selection and techniques for successful prosthetic treatment | 材料選択と臨床手技、咬合再建の要点 |
二日目は特に、治療後の経過を左右する因子への理解が深まる内容が多い一日でした。
1. 「長期安定」を生む補綴設計とは
印象に残ったのは、
「補綴物は“形をつくるため”ではなく、“機能を守るため”に存在する」
という明快なメッセージです。
人工歯は、ただ噛めれば良いわけではありません。
咀嚼効率、顎関節、咬合平面、筋活動、清掃性など、様々な因子が絡み合います。
日本包括歯科臨床(JACD)が大切にしている
「咬合・周囲組織・形態・機能の調和」
は、国が変わっても普遍的な評価基準であることを再確認しました。
2. インプラント治療は「入れた後」からが本番
インプラントの成功は、埋入の瞬間ではなく、維持できている期間で評価されます。
演者は、以下の点を強調していました。
- 過度な力を与えない咬合設計
- 粘膜・骨の厚みと質への配慮
- 患者ごとの清掃能力とリスク分析
- “患者と歯科医師が、メインテナンスを共に続ける関係性”
つまり、インプラント治療は「技術」だけでなく、
患者さんと医院の 長期的なパートナーシップの上に成り立つ治療なのです。
これは、私たちソアビル歯科が日々患者さんへお伝えしている
「治療はゴールではなく、スタートです」
という姿勢とも完全に一致していました。
3. 材料選択と手技は“目的”ではなく“手段”
午後の講演では、補綴材料・接着操作・形成デザインに関する具体的な考察が続きました。
しかし、そこでも一貫していたのは
材料や術式が「長期安定のための手段」にすぎないということ。
どの材料が良いのか、どの手技が優れているのか。
その答えは 患者さん個々の口腔内環境によって異なります。
ですから、私たち臨床医に求められるのは
「技術を増やす」ことだけではなく
“状況に応じて最適な選択ができる判断力” だと再認識しました。
■ 参加して感じたこと
海外の学会に参加すると、
“自分たちが大切にしている臨床の軸は正しいか?”
“どこに改善の余地があるのか?”
を客観的に見直す大きなきっかけになります。
今回、JACDで日々考え続けている
包括的診断・咬合理解・メインテナンスシステム
は、世界的にも有効で普遍的なコンセプトであると改めて確信しました。
そして何より、
「患者さんの未来のために学び続ける」
この姿勢こそが、歯科医療における**最大の“長期安定”**だと感じています。
■ 最後に
今回得た学びは、決して「目新しい手技」だけではなく、
“治療の本質に立ち返る”視点 そのものでした。
ソアビル歯科医院はこれからも、
誠実さと思いやりをもち、上質な歯科医療を提供する
という理念のもと、
患者さんの生涯の健康に寄り添う医療を続けてまいります。
また日々の診療で、直接お話させてください。