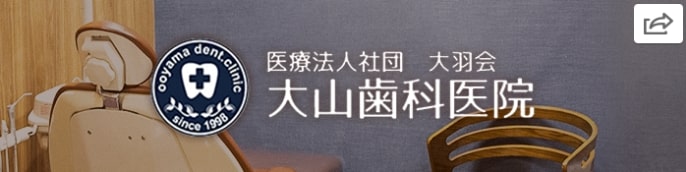🏔️ 朝5時スタートの筑波山──静寂と紅葉と、ほんの少しの誇り
朝5時。
まだ街灯が点き、空気が夜の冷たさを残したままの時間に、筑波山のつつじヶ丘駐車場へ着いた。弟と二人での登山は久しぶりだ。暗闇の中でヘッドライトをつけ、ザックを背負い直すと、すぐに足元の石段が始まる。寝ぼけた身体には容赦のない急登だが、不思議なもので、こういう苦しさは嫌いではない。

つつじヶ丘コースは、ロープウェイ沿いの比較的短いルートだが、序盤からしっかり登る。辺りはまだ薄暗く、鳥の声も聞こえない。時折すれ違う登山者のヘッドランプだけが、ぼんやりと揺れている。
静寂というのは、単に音がない状態ではなく、余計なことを考えずにいられる時間のことを言うのだろう。歩みがリズムになり、呼吸が深くなり、頭がどんどん軽くなっていく。


30分も歩くと、空の端がほんのり白み始めた。
「間に合いそうだな」
弟が小さく言う。
今日は日の出を山頂で見るつもりだったが、天気予報はギリギリ。雲が厚いかもしれない、と昨夜話していた。登山をしていると、自然の都合に従うしかない。間に合う・間に合わない、見える・見えない、その “どうにもできなさ” が案外心地よい。
中腹に近づくと、風が冷たくなり、あたりが急に開けた。つつじヶ丘から女体山に向かう岩場特有のゴツゴツとした地形が現れる。空は薄い紫からオレンジに変わり始め、水平線の場所がかすかにわかるほどの明るさになった。顔を上げると、すでに何人もの登山者が岩の上に陣取り、カメラを構えている。

山頂に着いたのは日の出の10分前。
視界に広がるのは、関東平野のとてつもない広さだ。街の明かりがまだぼんやり残り、その上に朝の薄い靄が流れている。東の空を覆う雲の隙間から、金色の筋が幾重にも伸びていた。息を吐くと白くなるほど寒いが、そのくらいがちょうどいい。身体が引き締まり、感覚が研ぎ澄まされていく。

そして、太陽が雲の端からゆっくりと姿を見せた。
誰かが「出た」と小さくつぶやく。
その瞬間、山頂にいた人たちの空気がふっと変わる。言葉ではなく、全員が同じものを見て、同じ時間を共有しているという感覚だけが残る。橙色の光が雲の裏から滲み出て、空は一気に赤に染まった。目の前に広がる景色は、写真で見るより何倍も深い。光と影の境界がはっきりしていて、世界が一つの絵画のようだった。
弟も黙ってその光景を見ていた。
言葉にしなくても伝わる瞬間というものが確かにある。
家族でも、友人でも、恋人でも、こういう時間を共有できる相手がいることは、実はとても恵まれている。

日の出が完全に終わると、山頂の人々はそれぞれのペースで動き出す。コーヒーを淹れる人、写真を撮り続ける人、すぐに下山を始める人。
私たちは風が強くなる前に下ることにした。岩場をゆっくり進むと、背中に当たる朝日が暖かい。先ほどまでの厳しい寒さが嘘のようだ。


下山途中、ふと足を止めた。
頭上に、まるで炎のような赤い紅葉が広がっていた。
筑波山の紅葉は場所によってムラがあるが、今年は冷え込みが早かったせいか、色づきが見事だ。赤、橙、黄色が重なり、風に揺れるたびに色が変わる。下から見上げるとまるで “紅葉の天井” だった。
弟も「これはすごいな」と珍しく感嘆の声を漏らす。

紅葉の中を歩いていると、季節が移り変わる速度を急に実感する。
夏の名残はもうなく、冬の気配がすぐそこまで来ている。
忙しく過ぎていく日々の中で、自然は確実に時間を刻んでいるのだと気付かされる。
つつじヶ丘の駐車場に戻る頃には、すっかり日が昇り、車も人も増えていた。
来週末は連休で混雑するだろう。今日の静けさは、ある意味で貴重だったのかもしれない。

帰りの車の中で、
「また来ようか」
と弟が言った。
その一言が妙に嬉しかった。登山というのは、景色だけでなく、こういう小さなつながりを思い出させてくれるのかもしれない。
早朝の筑波山は、心をリセットするのにちょうどいい場所だ。
朝の冷気、太陽の金色、鮮やかな紅葉、そして山を登るときの静けさ。
そのすべてが、今の自分にとって必要な要素だった。
またふらっと早朝に来ようと思う。次はひとりでもいいし、誰かとでもいい。
ただ、あの景色と空気に触れたい。それだけで十分だ。